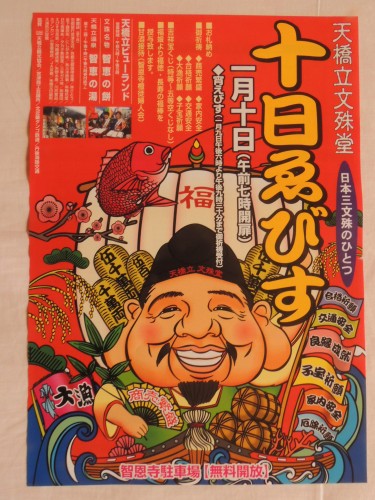ガイド部会 月ごとの定例研修。植物も磯の表情もその都度変わってきている。
浜の宝探し
海藻の生育状況 ウミトラノオ、ハバノリ(褐藻類)など
ハバノリは高級食材 丹後半島の京丹後市久僧辺りの集落では「ハバメシ」「味噌汁」など、ワカメと同じような用途。
更に、お年寄りにお聞きすると、宮津市波見では食べるが、すぐ近くの岩ヶ鼻では食べないようだ。
イタヤガイ(昔はしゃもじに使われた 左)、タカラガイ(真ん中の2個)、アズマニシキ(右の大小2個)
文珠貝(カガミガイ 左)、橋立貝(ウチムラサキ 右) 名前のとおり天橋立に生息
同内側










トハシダテガイ-500x375.jpg)








 朝日新聞 平成26年2月5日 掲載
朝日新聞 平成26年2月5日 掲載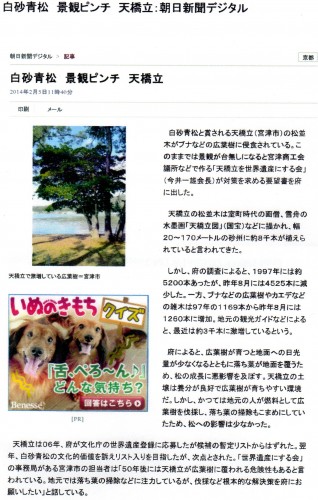


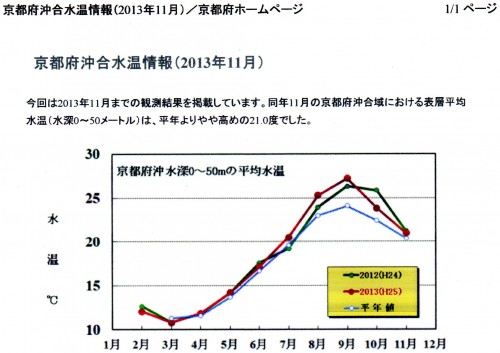
-500x375.jpg)