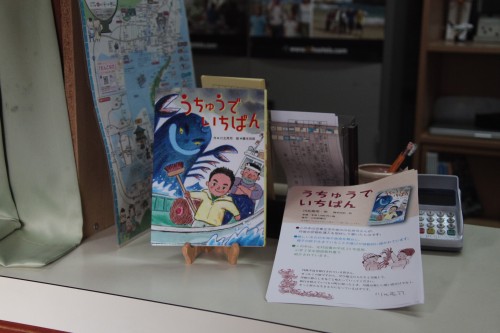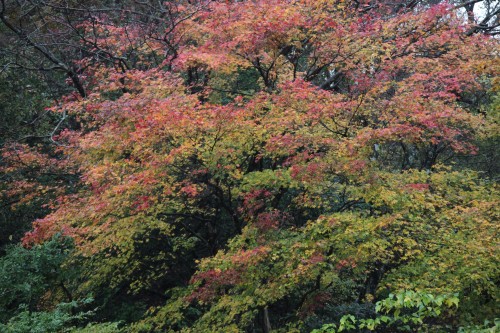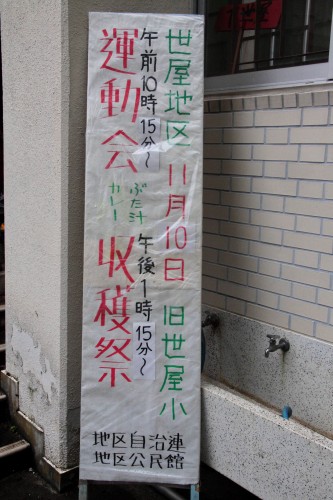「どうかしたのか」と長いつきあいのカメラを疑いました。虹を撮ったはずなのに、

♪七色の虹がきえてしまつたの♪と虹は(赤、橙、黄、緑、青、藍、紫)七色が基本のはずなのに、どう数えても七色がない!自分の目とカメラの認識が正常なら、今日の虹は不完全な虹だ!とも思いました。

しかし、話を聞いてみると、どうもとらえ方は必ずしも全世界一律に統一されているのではないと言うことなんですって。国や地域や時代によって、五色だ!といったり六色だといったり、あるいは二色だ!いやいや八色だと様々。五色というばあい(赤黄緑青紫)、六色というばあい(赤、オレンジ、黄、緑、青、紫)、二色のばあいは(赤、青)なんだそうです。カメラのせいでも虹のせいでもないのです(^.^) では、なのになぜ誰が「七」に固執したのかというとニュートンさん、「七」は落ち着きがいいから、縁起がいいからとおよそ学者らしからぬ理由なんだということ。

ちなみに、町を走る虹。

こちらは,赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の七色。「日本」の虹。
町を走る虹、ここにも!

五色です。おや!外から紫・緑、、? でも主虹と副虹が逆というのはあってるじゃないですか(^.^)
また、 万葉集の 「伊香保ろのやさかのゐでに立つ「努自」(ぬじ)の顕はろまでもさ寝を寝てば」 東歌 この歌の、「努自」(ぬじ)、これが「にじ」のこと。当時は通い婚制。「ああにじがかかるまで彼女といっしょにいたいなあ」という意味。漢字以前の日本人が、なぜ「ぬじ」と呼んだのでしょうか、、、謎はつきません。
おまけ。、雨粒の大きいときは色の濃い細い虹が見られます。
※虹はいずれも府中付近 撮影日時 2013/11/13 15:40ころ












 丹後は
丹後は