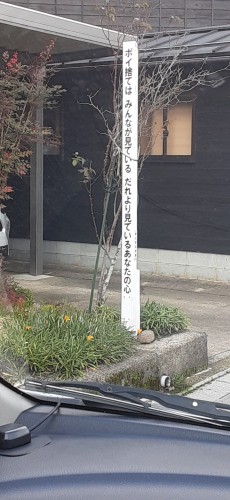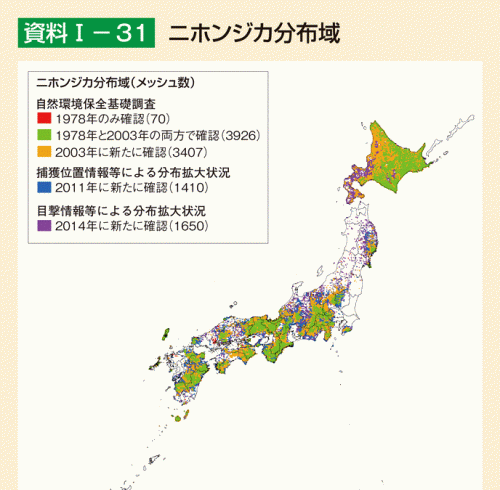ササのある光景、

これは上世屋の常識。しかし、シカの食害のために、ササがあるということが「日本の非常識」になる実態が進行中とのことです。
シカの分布域に関する環境省調査のまとめです。
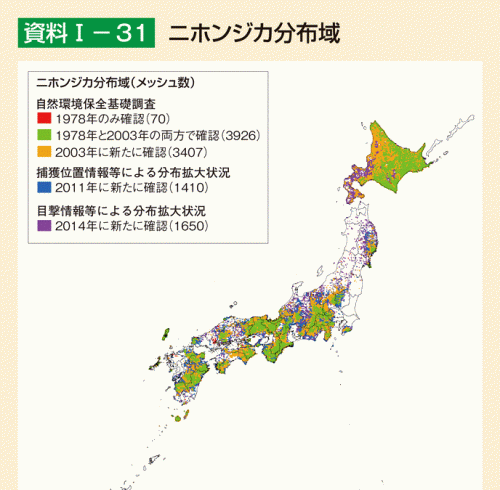
丹後半島域は、黄土色。つまり、姿が見えだしたのは2003年ころ。振り返ればこれは、あれ、シカが鳴いている、牡シカに出くわしたが逃げなんだぞ、などと言ってたのが、その頃です。

あれよあれよと言う間に増殖、森の下層の草や低木全ての葉や皮がシカの食事の対象ですから、半島の森はたまったものではありません。

そんな森の被害に関し、下草の代表ササについて、その現状の実態、問題点などをレポートしてくださっているのが『日本応用地質学会https://www.jseg.or.jp/chushikoku/assets/file/faq/3-08.pdf』。
シカの食害によって土壌侵食や表層崩壊が起きやすくなると聞きますが、なぜでしょうか。
環-8
シカの食害とは、シカの採食によって起こる被害の事ですが、増えすぎた二ホンジカによって農林業への被害と同時に自然植生の被害が問題となっています。この自然植生への被害は 1980 年代から深刻化し、図-1 のように今やシカの分布は太平洋側を中心に北は北海道から南は九州まで分布域が広がり、被害は南アルプスなどの高標高域にも及んでいます。
シカは草食の反芻獣で柔らかい草や落ち葉から堅い樹皮まで食べることができ、地域によって被害の対象は異なります。ササはブナ等の森林の下層植生として多くの場所で見られ、冬期にも葉をつけシカの貴重な栄養源となります。常にシカの採食圧のもとにある場所では、シカが好む植物が衰退し、シカが食べない植物や採食圧に耐性のある植物のみが繁茂するようになり、これを偏向遷移と呼びます。
四国・剣山系の三嶺一帯では 2007 年頃からミヤマクマザサやスズタケといったササ原が壊滅的被害を受け裸地化も進行し(写真-1)、樹皮の剥皮で立ち枯れの樹木も増えました 2)
(写真-2)。
その後ササにかわって群落を形成したのはシカが食べないイワヒメワラビやタカネオトギリ、シカの採食圧に耐性のあるヤマヌカボやイグサなどで、すっかり違った植生に替わってしまいました 3)。
写真-1 スズタケが枯死し林床は砂漠化(高知県香美市さおりが原 2016 年 4 月)
写真-2 枯死したウラジロモミの白骨林(高知県香美市白髪避難小屋東側 2016 年 11 月)

環-8
(2)ササの枯死と土壌侵食の関係
ササはその葉をシカに食べられても地下茎に蓄えられた養分のおかげで翌年の葉をつけることができます。しかし、シカの高い採食圧のもとではせっかく出た芽もシカに食べられてしまいます。そうなると地上部は枯れ、やがて今度は地下茎と根も枯れてしまいます
4)。
ササが健全な時には、ササの根系が板状根系層(草本類の根系や腐植土が一体となって広がる厚さ 20 ㎝前後の最も表層の地層)の中を縦横に張ってネットのように土壌を押さえているため土壌侵食は起こりません(写真-3)。しかし、2009 年頃にミヤマクマザサが衰退した白髪分岐南東側斜面では、ササの根系が枯れてこのネット効果が失われたために土壌侵食が起こる事が明らかにされています 5)。
写真-3 ミヤマクマザサの根系が見える断面と左上はその地下茎の節から出る側根
(高知県香美市白髪分岐南東側斜面、2017 年 6 月)

同斜面では勾配30°以上でシカの食害でダメージを受けた低木が傾くことで根が抜け上がりを起こし斜面走向方向に亀裂を生じ、その後ササ以外のイグサ等の植物がこの木の根元周りにつくことで根系の上載荷重が増し、一層樹幹が傾くことになります 6)。その傾きと反対側の根元は斜面から浮き上がり、そこに入り込んだ雨水は土壌を根系から洗い出してしまいます。さらに風の力が加わることで写真-4 のように短期間で低木が転倒してしまう事があります。抜けあがった根がはっていた範囲が裸地を形成することになり土壌侵食を加速させることになります。
シカの強度の採食圧のもとで 2007 年にミヤマクマザサが壊滅したカヤハゲでは、その後広い範囲で裸地化が進行しました。しかし間もなくヤマヌカボ群落が成立し緑が復活しました。ところがそのヤマヌカボ群落の根系マットに溝が形成されはじめ、小さく分割された根系のブロックが勾配 30°を超える斜面を滑り落ちて再び裸地化が始まりました(写真-5)。この事例はササが衰退した後に別の植物群落が復活して来ても、必ずしも元の安定した斜面に戻ったわけではないことを示しています。
環-8
写真-4 葉をつけたコハウチワカエデ(胸高直径 18 ㎝)の根が、2015 年 11 月にわずかに浮き始め、2016 年 9 月に完全に転倒、右下は転倒した根(幅 3.5m)を裏側から見た。
写真-5 裸地に成立したヤマヌカボ群落の板状根系層がブロック化して斜面をすべり落ち、土壌侵食が進行して再び裸地化する(高知県香美市カヤハゲ、2016 年 5 月)
環-8
シカの食害によりササが壊滅した山を通る林道沿いには、ササの根系によるネット効果を失った急斜面から大雨の際に崩れて土砂が流れ出したり、樹木が枯れて転倒し、大雨で土砂と一緒に林道脇まで流れ出したり、砂防堰堤を埋めたりとシカの食害のもたらす影響は防災上からも無視できません(写真-6)。
写真-6 ササが衰退し剥皮被害を受けて枯れた樹木が転倒する急斜面では、所々で表層崩壊が発生している(高知県香美市白髪分岐南東側斜面、2013 年 10 月
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

こういう現象が、丹後半島全域で起きているのです。
『同斜面では勾配30°以上でシカの食害でダメージを受けた低木が傾くことで根が抜け上がりを起こし斜面走向方向に亀裂を生じ、その後ササ以外のイグサ等の植物がこの木の根元周りにつくことで根系の上載荷重が増し、一層樹幹が傾くことになります 6)。その傾きと反対側の根元は斜面から浮き上がり、そこに入り込んだ雨水は土壌を根系から洗い出してしまいます。さらに風の力が加わることで写真-4 のように短期間で低木が転倒してしまう事があります。抜けあがった根がはっていた範囲が裸地を形成することになり土壌侵食を加速させることになります。』

上世屋の常識は日本の非常識、しかし、連日連夜「襲撃」を受けていますから、風前の灯火。
そもそも森林生態に影響を及ぼさない生息密度は、3~5頭/㎢。京都府の森林面積で試算すると、適正生息数約 10,000~17,000 頭なのだそうです。これに対して、生息密度指標や捕獲状況等を基に、生息数を推定するためのシミュレーションをしたところ、京都府全体での生息数は、令和2年度で約96,000 頭と推定された
《第二種特定鳥獣管理計画 ニホンジカ-第6期令和4年4月1日から令和9年3月31日まで)京 都 府 www.pref.kyoto.》
適正数の8倍から9倍が生育している、ということになるのです。
ササ文化は日本の伝統文化。それを産し伝承する里にササがなくなると言うことが起きようとしている、、ということです。ササ地からのSOS、さて、、どう受け止めたらいいのでしょうか、手を打つのは今!

官行民の連携、これしかササ地の保護保全は道はないのですが、、、。