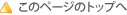職人から職人へ、技が渡る瞬間。

お題は、ススキ活用。

そのススキは、イノシシやシカの団地だと迷惑がられているのが、現状。また、丹後山間部では屋根をササで葺いていましたので、あまり注目されません。
しかし、そのススキ、二つの点で、里山生活の重要素材でした。一つ、炭俵素材。二つ、雪囲い素材。どちらも今は紙袋やビニールトタンに置き換わって当たり前になっていて、伝える方もいらっしゃらなくなっています。里山の暮らし文化を学ぶうえで、気づかない盲点だったのです。ここに焦点をあてて企画したのは、美山の茅葺き職人、大下倉君。伝えてくださったのは、「上世屋・おふくろの森」主催者の吉岡徳雄さん。
刈ったススキの束は、集めて立てて、さらに乾燥させるとのこと。
セヤ高原では、屋根でなく、雪囲いに重宝されたのがこのススキ。
このススキ講座、来春に引きつづきます。ご注目ください。
世屋川流域エコミュージアムサービス・「生物多様性世屋川流域センター」・宮津世屋エコツーリズムガイドの会が、お手伝いします。
さて、12月。
さっそく、丹後に北からの「白い封筒」が届きました。