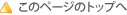おー イノシシ 、しかも、ウリボウを連れて、、、
豚熱が日本で再流行したのは2018年。豚熱発生前後のイノシシの相対的な個体数の調査があるそうです。
岐阜大学 応用生物科学部附属野生動物管理学研究センターの池田敬特任准教授と同学部の鈴木正嗣教授、淺野玄准教授の研究グループは、岐阜県環境企画課と協力して行ったカメラトラップ調査で、豚熱発生前後の郡上市、下呂市、高山市におけるイノシシの相対的な個体数が急激に減少したことを把握した。という話です。
その数字。
「2017年で最も高く(100日当たり8.88頭)、その後継続的に明らかな減少を示し、豚熱発生後の2019年で最も低い値(100日当たり2.03頭)を示した。」
つまり、この間の生存率22%、致死率78%。
ここしばらく、イノシシの「公共事業」が見られないなと思っていましたが、自然の掟とはいえ、日本イノシシは殺人的な感染被害の渦中にあったのですね。
シカは草や低木を食べるシカ、地中の根や塊茎を掘り返すイノシシ、森林の植生を変えたり、土壌を変えたりします、その食害は脅威ですから、、減ったからいい、もっと減らないかというものではない、と、家畜専門の獣医さん、 野生動物と家畜との間で広がについてについて、こんなお話をされています。
、、、、、、、、、、、、
1)豚コレラ
病原は豚コレラウイルス(Flaviviridae, Pestivirus)であり、ブタとイノシシのみが感染する。伝染力が強く、高い致死率が特徴で、唾液や糞中に排泄されたウイルスと接触することにより感染が拡大する。特異的(病気と診断するのに特徴的)な症状はなく、発熱や食欲不振、下痢や後肢麻痺が認められる。治療法はなく、摘発淘汰によって感染拡大を防いでいる。なお病名中に「コレラ」とあるが、これは「コレラの様な下痢症状を示す」ことから付けられたものである。(ヒトの「コレラ」はVibrio choleraeという細菌が原因である)。また2018年に豚コレラが国内発生したのと同時期に、中国で「アフリカ豚コレラ」の発生があった。アフリカ豚コレラは豚コレラと同じ様な症状を示すが、原因のウイルスの種類が違う。よく混同されるので、注意が必要である。

2)肝蛭(かんてつ)症
吸虫に分類される寄生虫で、反芻獣を中心に感染する。反芻獣の糞便中に虫卵が排泄され、ヒメモノアラガイという貝を経由し水草に付着し、それを反芻獣が採食することによって感染が広がる。症状としては食欲低下、削痩や貧血が認められ、特にヤギやヒツジでは重篤な症状を示す場合がある。
私は過去に肝蛭に感染したヤギを診察したことがあるが、貧血がひどくすぐに死亡してしまった。このヤギは山際近くの屋外で、水路のある囲い(壁1m程度)の中で生活をしており、おそらく侵入してきたシカが原因で感染したものと考えられた。奈良公園のシカの検査では87.5%のシカから肝蛭の虫卵が検出されていることが報告されている。畜産関係者の間では過去の病気のイメージがある感染症だが、シカの個体数が増えている現在、再注目すべき疾病の一つである。
3)伝染性嚢胞性皮膚炎
家畜では主にヒツジやヤギに感染する病気で、ポックスウイルス科のオルフウイルスを原因とする。症状としては皮膚に丘疹や水疱を形成する。野生動物ではニホンカモシカでの感染が散見される。とくに顔面に水疱が形成されやすく、口の周りや口の中に病変ができると採食困難に陥り死亡に至るケースもある。ニホンカモシカの抗体陽性率は32〜39%という報告があり、1976年に秋田県で発生が確認されて以降、2013年には京都府まで南下していることが確認されている。本症はヒトにも感染する人獣共通感染症であり、家畜伝染病予防法の中では届出伝染病に指定されている。
4)その他の感染症
この他に野生動物と家畜の間で注目される感染症として、サルモネラ感染症がある。サルモネラは腸管内に存在する細菌で、血清型で2,500種類以上ある。北海道の野生動物を対象としたサーベイランス調査においては、カラス類、カモ類、キタキツネやアライグマから家畜に感染しうるサルモネラ菌が見つかっている。中には抗生物質に耐性を持つ菌も見つかっており、家畜から野生動物への感染が疑われる事例もある。
また2010年に宮崎県で発生した口蹄疫も、シカやイノシシにも感染する疾病である。この時はシカやイノシシへの感染は確認されていないが、感染していれば豚コレラのように他県への拡大があったかもしれない。
、、、、、、、、、、、、
「人獣共通感染症」!こんな言葉があるんですね。茂みにきえていった親子イノシシ、あらためて、人もシカもイノシシもみんな生態系で繋がり相互に作用しあう仲間として、頑張れよ、無事に大きくなれよ、と声をかけたくなりました。