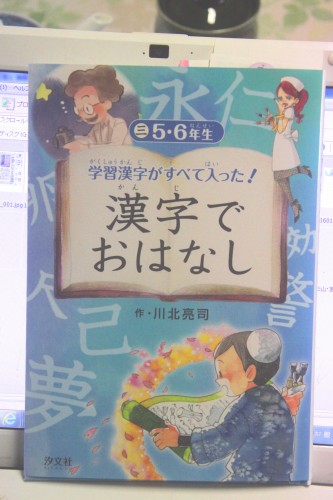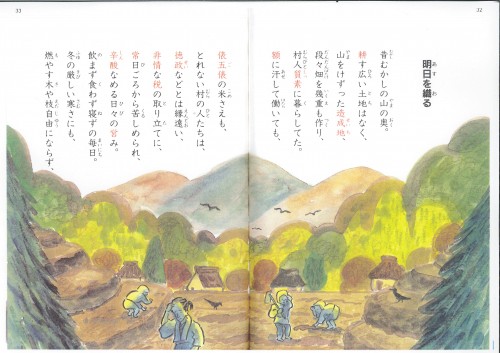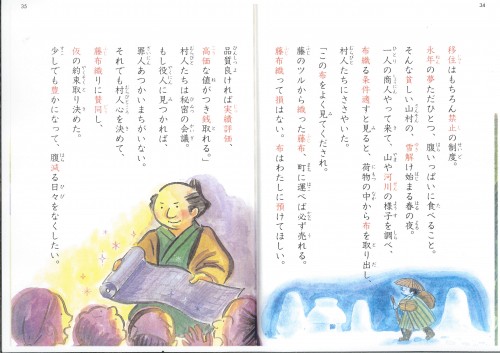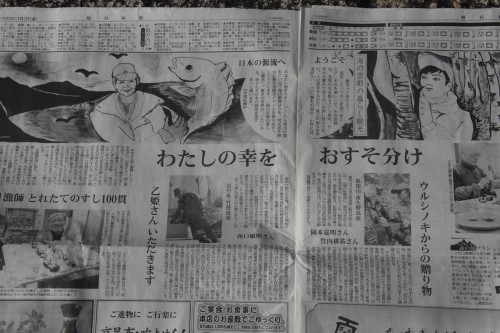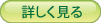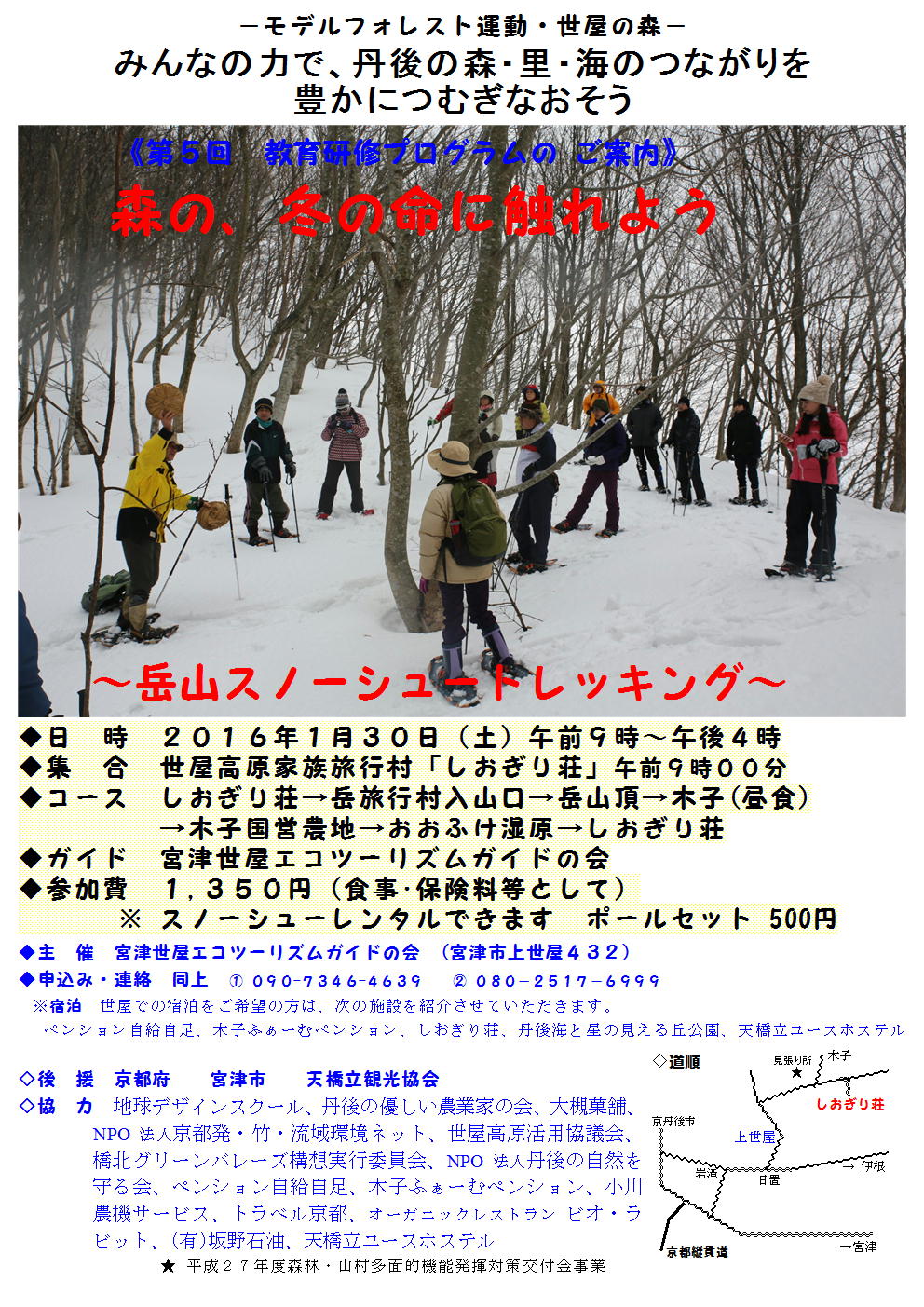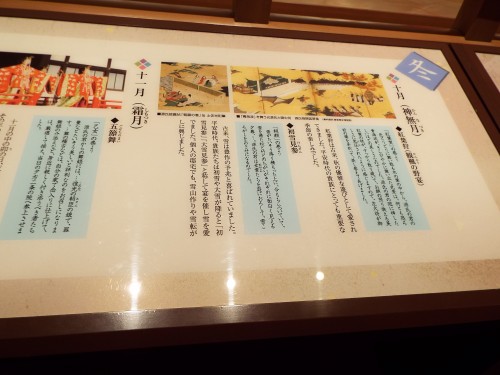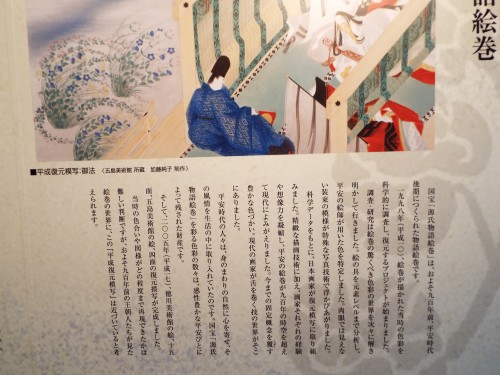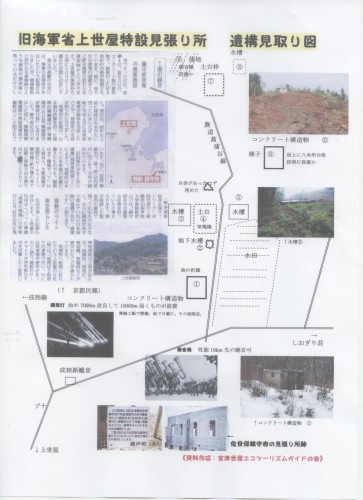「Prediction and impact assessment of the changes in suitable habitats for beech (Fagus crenata)forests under climate change scenarios」
■ prediction 予想、予測 ■ impact assessment 影響評価 ■ Fagus crenataブナ ■Beechブナ属 ■climate change 気候変動 ■scenarios 計画を実現するための筋道。 ■suitable for に適した ■habitat生息場所、、、訳すと、温暖化にともなうブナ林の適域の変化予測と影響評価

国立環境研究所や 地球環境研究センターなどによるこのレポートの結論は、「森林を構成する樹木の移動速度は4~200km/100年のオーダー、温暖化にうまく適応できる植物もあるが、ほとんどは温暖化に追いつくことができない。本州の日本海側では夏期の高温によってブナ林の分布が制限され、適域が高標高地域へ上昇しながら9%~ 42%に減少する。実際にブナ林かつ適域である地域は、3%~ 40%に減少する。」というのが結論。ブナは事態に適応できないだろうとの厳しさをつげています。
ところで、「燃える樹」という詩を みずかみかずよさんが書いておられます。※あゆみ出版「こどもといっしょに読みたい詩」。~樹がかまどで燃える炎をうたった、、、ノーノー!~詩では「樹」という言葉が題も含めて六回用いられています。まさしく「樹」賛歌。

さて「樹」と書いてあるそれを温暖化に適応出来ないとされる「ブナ」に置き換えて読んでみました。そうしたら気づいたことがあるんです。まずはまあ、「樹」を「ブナ」に置き換えてよんでみましょう、、
「燃えるブナ(樹)」
どっしりと 根をおろしたまま
もうどこへも 行けない
ブナ(樹)はブナ(樹)であることを生きている

深く足を踏ん張り たかく胸をふくらませ
ひろく腕をのばしながら
百年も千年も
いのちをあたらしく
いのちをふかめてきた

ブナ(樹)も人も思う心は同じ
春には若葉でわらい
夏は茂ることですずしい
秋はもみじした葉が美しく舞うし
冬にはすっぱりはだかになって自分をみつめる

寒風にふるえながらも
地底のあしうらから
天をさすほそい指さきへ
いくすじにもわかれて
たちのぼる
いのちのぬくみをだいている

くらやみに
しんしんいてついて立つブナ(樹)
無心なブナ(樹)よ
芯で燃える
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
すてきなブナ賛歌の詩です。樹になれ ぶれるな 人生は信念の一本道ぞ それを 樹に、とりわけ冷温帯の落葉広葉樹に喩えてとかれているのです。

これはブナにおきかえましたがけやきでも。しかしつばきやタブではいけない、「冬にはすっぱりはだかになって」iはなりません。森や樹と精神文化は深く結びついている一つの例です。温暖化というのは温暖化にともなうブナ林の適域の変化予測と影響評価ということだけにとどまらない文化の破壊だということに気づきます

ブナ君、、、すまん、、、というより私たち自身にとってかけがえのないものをうしなうことになるとんでもないこと、温暖化阻止に向けてあなた方が燃えなければだれが燃える?そんなことをブナはいっているように思いました。この詩から教えられたことは大きいです。