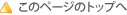ちょっとしらべなわからん、ちょっとしらべたかがわかるもの「試験問題」にちょうどいい 、その代表のようなもの!

オシャクジテンダ!うちのパソコンなんか、もう「お酌事典た゛」とて゛てきます。
なんだそれ、、、シダです、和名か 和名です、、デンダとはシダの古名、オシャクジ!どういう意味?
出回っているコピーは多くが、おしゃくじのジを「寺」ととらえたおしゃく寺ってところでみつかって、でそのお寺は、どこにあったかは、不明です、、、。このレベルだと調査不足ということ(^.^)。
さて、それを光田重行先生※世屋の植物観察会講師先生 が、明快に軽妙に説明。
「温帯系のシダですから京都には中・北部にやや普通にありますが、故郷の四国では見た覚えがありません。九州でも稀では? 喜びひとしおでしたね。
「社貢寺という寺はない」というのは、東大教授だった前川文夫の論考です。だれが社貢寺説を言い始めたのかはっきりしませんが、民俗学的な常識からすれば、これはオシャグジ様(ミシャグジ様)という民間の神さまに由来することはあきらか。東京に石神井(シャクジイ)があるように、左口神(さこうじん)とか宿神(しゅくしん、しゃくしん)と名前を変えながら、広く残っている神さま。塞神(さいのかみ)とクナド神(道祖神)を合わせたような神格であり、流浪芸人の神でもありました。オシャグジ様のほこらにある古木にでも着いていたことにちなむのでしょう。
オシャグジデンダの初出は、江戸期の小野蘭山の本草綱目啓蒙と思われますが、日本独自の本草学を目指して各地を旅した蘭山のこと、どこかの地方名を書きとめたのでしょう。それが木曽だったのかもしれません。 偶然でしょうが、小野蘭山の墓誌は、東京の石神井公園文化館に保存されているそうです。」
※オシャクジデンダ – 花の日記nannjyamonnjya.blog68.fc2.com/blog-entry-1880.html より
みんな名を持ちます、スギだ、カキだ、タケだ、どうして?いつ頃だれがどうして、、植物和名はポエジー、語源由来探索が楽しいじゃないですか。
さて、オシャクジテンダ!のオシャクジとは、『ミシャグジ – Wikipedia』によると、
■塞の神(サイノカミ)=境界の神、すなわち、大和民族と先住民がそれぞれの居住地に立てた一種の標識であると柳田國男は考察している
■「ミシャグジ信仰は東日本の広域に渡って分布しており、当初は主に石や樹木を依代とする神であったとされる。地域によっては時代を経るにつれて狩猟の神、そして蛇の姿をしている神という性質を持つようになったと言われている。その信仰形態や神性は多様で、地域によって差異があり、その土地の神や他の神の神性が習合されている場合がある。信仰の分布域と重なる縄文時代の遺跡からミシャグジ神の御神体となっている物や依代とされている物と同じ物が出土している事や、マタギをはじめとする山人達から信仰されていたことからこの信仰が縄文時代から存在していたと考えられてい」る。
縄文時代からの土地神様 仏教を携えて渡来した新民族と旧居住民族との葛藤と融合の歴史をつたえる神様、そういうことになると、俄然興味が湧いてきます。