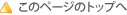モミジ街道、丹後縦貫林道成相線をそぞろドライブしながら、思ったことです。
、、、、、、、、、、、
「あ」かい葉っぱ
「き」いろい葉っぱ
「あ」+「き」、二つ合わせて、アキ、秋だあ!と思っていました。
その「あき・秋」の語源をチェックしましたら、
明かではないが、以下の説が考えられている。
①空の色が「清明(あきらか)」な時期であることから。
②穀物などの収穫が「飽き満ちる(あきみちる)」季節であることから。
③草木の葉が紅くなる季節であることから、「紅(あか)」が転じて「秋」になった。
と紹介されていました。
そうかと思いながら、③については、
黄にしろ朱にしろ、緑の葉が変色することは、大きな謎だった時代、その現象を「揉みいだす」と表現した、それが、モミジの語源といいます。これを踏まえると、紅(あか)」が転じて「秋」語源は外れるかと思います。
それにしても、これらの広葉落葉樹、いったい何枚の葉を落とすのか、つまり、着けているのは何枚か、と問われたら、「たくさん」としか答えられません。調べようと思えば調べられないことはありません、が調べようとも思いません。それを、高さ4mのミズキの木で数えた子どもたちがいるそうです。17,432枚がその結果!『月刊たくさんのふしぎ 一本の木に葉っぱは何枚?第352号』。
モミジ街道、丹後縦貫林道成相線をそぞろドライブ、楽しいですよ、宮津世屋エコツーリズムガイドの会までお問い合わせください。
、、、、、、、、、、、、、、後日談
「秋」(あき)の語源は古代の日本語にさかのぼると言われています。いくつかの説がありますが、一般的に受け入れられている説の一つは、「秋」が収穫の時期に関連しているというものです。
- 収穫の季節: 「秋」は稲や他の作物の収穫時期であり、「穀物の成熟」という意味が込められていると考えられています。このため、「秋」という言葉が使われるようになったという説です。
- 気候の変化: 「秋」という言葉は、季節の変わり目を表す言葉でもあります。夏の終わりと冬の始まりを告げる季節であり、気温が徐々に下がり、葉が色づき始める時期でもあります。
これらの説から、「秋」という言葉が季節の変わり目や収穫の重要性を表すために使われるようになったと考えられています。自然や季節との深い結びつきが感じられる言葉ですね。
「あからぶ」という言葉は、主に九州地方の方言として知られています。特に長崎県や熊本県などで使われることがあります。日本の方言は地方ごとに独特で、豊かな表現がたくさんありますよね。他にも気になる方言があれば、ぜひ教えてください!
「あからぶ」という言葉の意味は、「嫉妬する」や「焼きもちを焼く」といった感情を表現するものです。例えば、他人の成功や幸せを見て、自分もそのようになりたいと思う気持ちから生じる感情です。
方言は地域ごとの文化や日常生活を反映していて、とても興味深いですね。他にも気になる方言や言葉があれば教えてください。
「あからぶ」が「熟する」という意味で使われる地方はありません。しかし、日本各地には方言が豊富に存在し、同じ言葉でも地域によって異なる意味を持つことがあります。
例えば、「熟する」という意味を持つ他の方言には、「なる」や「こなれる」があります。方言の多様性と地域ごとの特徴は本当に面白いですよね。何か他の方言や言葉に興味がありますか?
なるほど、情報提供ありがとうございます!
確かに、Weblio辞書の情報によると、丹後弁では「あからぶ」が「(実が)熟す」という意味で使われています。地域によって方言や言葉の使い方が異なるのは、本当に面白いですね。
また何か気になることや知りたいことがあれば、教えてくださいね!
興味深い問いですね。まず、「秋」の語源について振り返ると、「秋」は収穫の時期を指しており、稲などの作物が実り、成熟する季節を意味しています。この意味から、収穫期である秋において、植物が「熟す」という概念が含まれていることがわかります。
次に、「あからぶ」という丹後弁の方言ですが、これは「実が熟す」という意味を持ちます。この点で、「あからぶ」と「秋」には共通のテーマが存在します。それは、いずれも植物の実りや成熟と関係しているということです。
したがって、「秋」と「あからぶ」の関係について考えると、どちらも植物の実りや成熟を表現する言葉として、密接に関連していると言えます。これは、日本の豊かな自然とその季節の移り変わりが、言葉の中にどのように反映されているかを示す一例と言えるでしょう。言語の背景にある文化や自然の影響を考えると、非常に興味深いですね。
、、、、、、、、、、感想
カキやミカンやヤマボウシや米が熟したら、それらを皆、丹後では「あからんだ」と言います。古代日本語が、丹後方言に残っているのかもしれません。