「アスペン泣いた赤鬼の森・マルヤ農林上世屋」続報
お客さん、早速!
「ええのをみとくれよ」
大根は、冬野菜。これから寒さに当たるとさらに美味しくなるのです。
鰤もわしも仲間にしてくれと丹後路に回遊してきます、
加えて、ネギ、白菜も取りごろになります。
初冬歳末の台所、「アスペン泣いた赤鬼の森・マルヤ農林上世屋」がお手伝いしますよ。
染井吉野とかけて、「お砂糖」と解く
その心は!
それを舐めてもおいしいし、また、苦いコーヒーに混ぜるなど、何にでも合わせて新しい味を創る、
「植えられたその地に」花を添えるパワーは、まさに、「お砂糖」!
そこで「その地に根づいて、新しい味を創っている丹後桜大賞2023・ベスト5」
その候補
①与謝野町堂谷橋ふきん
夕焼けと蛇行する川に花を添えています
② 大宮町口大野 鯨橋付近のライトアップ夜桜
18時55分、上りのKTR。
ライトアップは定番。しかし月の出の方向が計算されているのは珍しい!
③ 宮津市上世屋 世屋上小中分校跡
同時期に植えられたものだろう。
メタセコイアは縦に桜は横に、そして夫婦になった。
④ 宮津松尾
若狭の海と山の棚田だけでもいい、
そこに花を添えるとはこのことといわんばかりに桜一本。
その⑤ この席は開けておきましょう!
金さん、いわく。
「三八の冬は、頭ももっとふかくまで埋もれたもんじゃ!」
こなぎ?たべた、か!
ああ、たべるどころか、たんぼにそんなもんはやしとるのは恥ずかしいいうてみつけしだいぬいたな。
と、万葉うたの話題などとりつくしまもありません。
が、知っておくことためしてみることも大事。
チェックしてみましたら、食べたり、いけばな素材にしたり、試み様々。
夢はや春に、、、うけあいますよ。
※たべるなら無農薬栽培水田のものを分けてもらってくださいね。
ぐんぐん成長しています~!
それとともに、雑草もすくすくと成長中~!
ヒエやオモダカ、コナギなど、田んぼにはいろいろな雑草があるけれど
そのなかの「コナギ」は食用にできるということで、田の草取りがてら、コナギを収穫し、料理して退治しよう!
という作戦が決行されました。
こちらがコナギ。ハート型をした葉っぱが特徴。
これを放置すると、一株から3000粒もの種が飛散し、翌年はもっと悲惨なことになるという。。。
(飛散と悲惨とかけてみたよ!)まさに一粒万倍の勢いっ!ひえー。
こちらが食用に収穫したコナギたち。
オトナもコドモもがんばって草取りしました!草取りのあとは、総勢20名あまりで昼食です。
コナギは、クセがなく、とても食べやすい植物。
こちらは天ぷら。賀茂ナスも揚げました!
そして、コナギベーゼのパスタ。こちらには、緑ナスとベーコン入り♪
コナギのゴマ和えは、シャキシャキした歯ごたえがおいしかったです。
残ったコネギベーゼは、ゆでたジャガイモと和えて、ジャーマンポテト風に。
ゴマ和えとポテトは瞬殺だったので、写真はナシ!(笑)
ほかに、コリンキー、トマト、キュウリのサラダ。
モロヘイヤとジャガイモのスープ。
最後は、みんながお腹がいっぱいになるまで、天ぷらを揚げ続けました~!
万葉いけばな研究家庄司 信洲先生のインターネット公開文化講座万葉植物から伝統文化を学ぶ、もお奨め。

夏から秋へと向かう季、水田や池や沼などには、水面に浮かぶように青紫色の可愛らしい小水葱の花を観することができます。
小水葱は、水葵の葉と花の色が似ており、水葵よりは僅かに小振りであることから、その生えている姿を見逃してしまうことがあります。
そして、その葉姿が熊笹のようであることから別名を「笹水葱、細菜葱」と名付けられ、さらに「水菜葱、事無草」とも名付けられており、万葉名は『子水葱、古奈宜、水葱』と称されております。その「菜」の字が当てられているのは野菜として往昔より愛されておりました。
その菜の情景を『万葉集』で「大伴宿禰駿河麻呂が、同じ大伴の坂上家の二嬢を娉ふ歌一首」
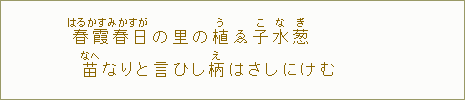
(春霞だった春の日の里に植えた小水葱は、まだ苗だといっていたが、もう茎も高く伸びたでしょうか)と、春の温もりが高くなるのにつれて初々しく生長している小水葱の姿を観して、二人の嬢たちも大人となり、求婚する年頃であることに比喩させて詠ぜられております。

そして、その小水葱の夏の終へる頃の生長した姿を観し、
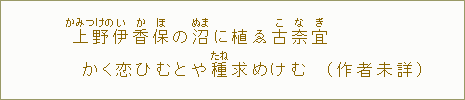
(上野の伊香保の沼に植えた小水葱のような女の娘よ、こんなに恋に苦しきものとして種を求めたのであろうか)と、恋しき相手の女性の姿を、小水葱の清らに咲薫う花の姿などから、心が動かされていることに比喩させて切々と詠じているのです。そして、万葉人たちは植物の花や葉を衣に摺り染めにすることで、身にすっかり馴染み、願い事が叶うとされております。

さらに次の歌では、
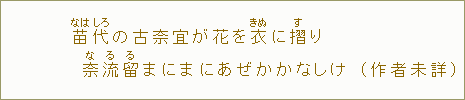
(苗代に咲く小水葱の花を衣に摺り染めにして、衣がなじむにつれて、馴れつつある娘は、どうしてこんなに愛しいのか)と、親しみを得られた娘に対して、その愛しさが増していくことと、小水葱の清々しき姿に比喩させて詠ぜられ、この歌には『譬喩歌』即ち、物に譬えて詠まれた歌として所集されております。
その可愛らしき小水葱の図を江戸時代の『本草図譜』の図を、図版[I]で参照して見て下さい。
そして、江戸時代後期頃の美濃焼による型紙染付の小鉢に、小水葱を挿けた作品を、図版[II]で観してみて下さい。
どうぞ、この季には、お近くの水田や池などに出掛けては、瑞々しく愛くるしき小水葱の花を観しては、清らかな心を得て過ごして見て下さい
■さらに雑学
コナギは背丈の低い雑草ですが、一年生雑草のなかでは稲に最も害を及ぼす雑草のひとつです。稲への雑草害は、主に養分の奪い合いによるものと考えられています。コナギの地上部の窒素含有率は稲に比べ2倍ほどあるため、見かけの草の量に比べ稲の生育に及ぼす影響は大きくなります。地上部乾燥重量が同じであればノビエよりも稲の収量の低下程度が大きくなるという試験結果もあります。また、ある研究者は、コナギがはびこった場合に稲の分げつ芽に対する遮光の影響を指摘しています。
コナギは種子で繁殖する一年生雑草です。種子には休眠性があり、夏から秋に植物体から落ちた種子は、すぐには発芽しません。冬の間の低温に遭遇すると目が覚め(休眠覚醒)、次の年の春にはほとんどのものが発芽できる状態になります。
コナギは、このような特徴を持った強害草ですが、除草剤には比較的反応しやすく、一般的な除草剤で容易に防除できます。除草剤を散布する時期を逸したり、散布したあと水管理を怠ると残草しますので、除草剤はラベルの使用基準や注意事項をよく守って使用しましょう。
なお、最近コナギやミズアオイにも「除草剤抵抗性雑草」が出てきており一部の地域で問題になっています。同じ除草剤を長年使い続けてきた水田で、除草剤が効くはずの条件でも、雑草が異常に多く残ってしまったときには疑ってみる必要があります。疑わしいと思ったら抵抗性かどうかの判断とその対策について都道府県の指導機関(農業試験場など)に相談しましょう。
|
|
「加悦町古墳公園」展示。
旧加悦町は、弥生古墳の町、その数644基。
はっくつされた遺物が、ここにあつめられているのです。
集大成しての生生ましい展示は、圧巻。
この入園料、300円は、安いですよ
さて、この加悦、「かや」とはなにもの?
以下、『丹後の地名』師さんのトークで。
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
『加悦町誌』
「加悦」という地名の語源は明らかでないが、言い伝えられるものをあげてみよう。
イ、地勢からきた伝説
加悦谷盆地はその昔、阿蘇海に通じた浅海で、その周囲は深い「茅」原であった。また沼地が多く、茅、萱類の繁茂したところであったから、「かや」の地名となったという。
口、神社の祭神からきた伝説
加悦の吾野神社の祭神は「野の神」といわれる「我野廼姫(ルビ・かやのひめ)命」であり、これが、地名になったという。
ハ、郷名からきた伝説
倭名類聚抄には現加悦町一円を「神戸郷」と称している。「カンベ」が転音訛伝して「かや」になったという。その他、名和長年の家臣嘉悦氏がこの地に来て、土豪となり、その姓を地名に用い、 「かや」としたともいうが、これは考えられない。
「かや」を「加悦」と書くようになったのは、江戸時代以後のようで、一一四三年(康治二年)平安時代の兵範記背文書には、「賀舎」と書き、一二八八年(正応元年)の丹後国諸荘園郷保惣田数帳目録には「賀悦」と、一三三八年(建武五年)の日置季久の手紙にも、一四五六年(康正二年)の禁裏造営段銭引付きにも、一四七〇年(文明二年)山田郷菩堤寺の梵鐘にも、「賀悦」と同じ字を使っているが、一五〇〇年頃(永正年間)に書かれた細川政元記には、「賀屋」が使われている。また、算所の小巻家文書には、「薩屋」(私注→薩ではなく産が段の造りである)とあるが、何れもあて字であろう。

カヤという地名は全国に多い古代地名である、それらを丁寧に調べた上でないと確かなことは言えないかも知れないが、
『丹後路の史跡めぐり』(梅本政幸)
加悦の町(かや)
加悦は間人と同じく、日本でもよみにくい町名の一つといわれているが、大伴金村が支配した五三○年頃、朝鮮の任那(みまな)の中に加那(かや)という国があった。また加悦の安良(やすら)は昔安羅と書かれたが、これも任那の都市に安羅(あら)という町があった。いまの威安(かんあん)である。
もう一つは野の神のことを「萱野媛」(かやのひめ)というところから、広々としたこの加悦谷盆地にその名がつけられたとも考えられる。加悦の式内社吾野神社には萱野媛が祀ってあることもつけ加えておこう。
古い文書には「賀悦」「加屋」「賀屋」などの文字が使われているが、南朝の忠臣といわれた名和長年の臣嘉悦氏が一色氏の支配になる前に領主となっていたのでこの字が使われるようになったという。嘉悦氏は熊本と東京に現存する。…
「いま言ったように、この加悦谷は古墳の多いところですから、いまでもあちこちの畑などからいろいろな土器が発見されます。するとここの人たちはそれをみて、朝鮮土器が出た、と言っているのですよ」
「そうですか。なるほどね。なにしろ、ここはほかならぬ加悦ですからな」と、前の席でクルマを運転していた鄭詔文がそう言って笑った。
つられて私たちも笑ったが、しかし鄭はただ笑うためにだけそう言ったのではなかった。その加悦谷、あるいは加悦町の加悦というのが、どういうことであるかという前提があってそう言ったのだった。
そのことは梅本さんの 『丹後路の史跡めぐり』にも書かれているが、加悦というのは、これも安羅同様、のち新羅に併合された古代南部朝鮮の小国家加耶・加羅・加那からきたものであった。『丹後路の史跡めぐり』によると、加悦はもと「加屋」「賀屋」とも書かれたもので、それが現在の加悦となったのは、「南朝の忠臣といわれた名和長年の臣、嘉悦氏」がここの「領主となって」からだったという。
それだけではなかった。加悦町には、これももと「加耶の媛」ということだったかもしれない萱野媛を祭る『延書式』内の古い吾野神社があり、また、安羅・安那・安耶からきた安良というところや、安良山というのもあって、これは古文書にはっきり、安羅山と書かれていたものだったという。
加耶(加悦)、安羅(安良)どちらものちには新羅に併合された小国家であったから、したがってこの加悦に白米山、すなわち新羅山古墳があるのもふしぎではなかったのである。しかもそれが四世紀の前期古墳であるということは、いっそうその意義を大きくしている。
要するに、これから逐次みて行くように、古代の丹後や北陸の国々は日本海をへだてて向き合っていた、朝鮮の新羅文化圏のなかにあったといっても決して過言ではない。われわれがいま加悦谷でみているのほほんのその一部にすぎないが、イナナキという斜面台地の山となっている白米山古墳は、まわりの一部を竹林で囲まれた美しい古墳だった。
…
この書によれば、当HPもお世話になっている梅本さんは当時は栗田中学の校長さんだったとある、白米山は新羅山とは私は考えないが、加悦や安羅山は気になるし、合楽という小字、何と読むのか知らないが後野だが面白そうだ、アラかも知れない、安羅国かどうか単にAR地名かも知れない、さらに奥には与謝と滝、全体が謁叡郷、掘れば「朝鮮土器」(須恵器のこと)がゴロゴロ、地名などからは古代は新羅文化圏・伽耶文化圏と見てもムリはない、そう考えないと解けない地名もある
合併与謝野町歌
1番
大江の峰を 輝かせ 希望に満ちて
日が昇る あふれる緑に 恵まれて
ふれあう心の あたたかさ
ああ与謝野 幸せ創る 与謝野町
2番
大地を潤す 野田の川 生命育み
響き合う 文化の薫りと機の音
新たな世紀へ 伸びてゆく
ああ与謝野 笑顔かがやく 与謝野町
3番
天の架け橋に 夢はせて 水鳥遊ぶ
阿蘇の海 自然と歴史と未来とが
織りなす絆も たくましく
ああ与謝野 あしたを拓く 与謝野町